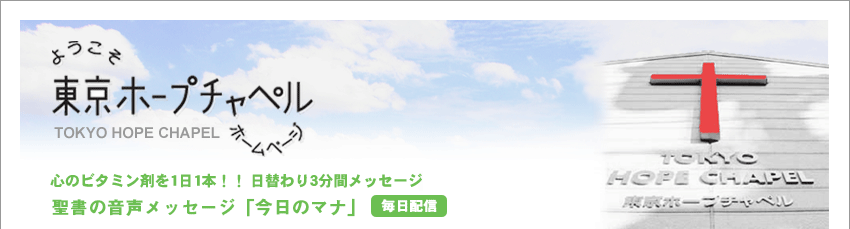2025.12.07
「ハヌカの祭り」 ヨハネの福音書 10章22節-23節 井上圭 伝道師
アドヴェント3週目に入りました。世界中でクリスマスを祝いますがイスラエルではハヌカというお祭りをします。光の祭りとも呼ばれ青を基調とし蝋燭に火を灯して歴史的戦いの勝利を祝います。
「そのころ、エルサレムで宮きよめの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中で、ソロモンの回廊を歩いておられた。」(ヨハ10:22-23)宮きよめの祭りは神殿奉献記念祭とも訳されハヌカの祭りのことです。ハヌカとはハナフから由来し奉献、献身という意味です。イエスもハヌカの祭りのタイミングでエルサレムに来られ神殿に入られました。歴史的経緯の中で神への冒涜があり、神殿が汚されました。それを清めるために燭台の火を灯そうと油壺を探しましたが一日分もありません。しかし灯してみると、8日間燃え続けました。その間に純粋な油を用意できたので宮清めが無事に行われました。そんなハヌカの祭りから3つのことを学びましょう。
第一にイエスが灯した光としての「ハヌカ」です。イエスの誕生は9-10月の仮庵の祭りの頃だと言われています。「ユダヤの王ヘロデの時代に…ザカリヤという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツといった。」(ルカ1:5)夫ザカリヤが祭司の役目を担った期間から算出すると、エリサベツが身籠ったのが6-7月頃でマリアはその半年後の11-12月、ハヌカの祭りの頃に受胎したことが分かります。ハヌカは光の祭りでありマリアのお腹に光が来られたのです。「…このいのちは人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。」(ヨハ1:4-5)「すべての人を照らすそのまことの光が、世に来ようとしていた。」(ヨハ1:9)光であるイエスがハヌカの祭りの日にマリアの元に来たのと同時にすべてのユダヤ人、全世界の人々の真の光、いのちの光となりました。「しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。…異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の陰の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。」(イザ9:1‐2)ガリラヤに真の光であるイエスが来られ福音がもたらされることが預言されています。また、ハヌカの燭台は9つに分かれており、1日1本ずつ火を灯します。「あなたがたは以前は闇でしたが、今は、主にあって光となりました。光の子どもとして歩みなさい。」(エペ5:8)私たちが光の子として歩んでいくことが神の御心なのです。
第二に闇に対する光の戦いとしての「ハヌカ」です。ハヌカは戦いに勝利して祝われた祭りです。私たちは光の子として暗闇と戦う者です。私たちは光の子とされました。私たちを造り変えて下さったイエスを通し、福音を告げ知らせるために生かされています。現代も暗闇の力は絶えず働いています。私たちは肉体や精神で戦うのではなく、神の武具で戦う必要があります。それは御言葉の剣です。イエスも荒野でサタンに御言葉で戦い勝利されました。御言葉を絶えず携え御言葉をもって勝利することが出来ます。イエスは休むことなく天の父と共に闇の力と戦い続けています。私たちも光の子どもらしく主の光を輝かせ闇に打ち勝つ者となりましょう。
第三に信仰的献身としての「ハヌカ」(再献身)です。今日の聖書個所でイエスは宮清めのためにエルサレムの神殿に上ったとあります。ハヌカとは献身であり聖別です。イエスを信じる私たちは聖霊が住まわれる神の宮です。ですから神の神殿とされた私たちは絶えず主に献身し主の前に清く歩んでいきましょう。ヨナは主に背いて別の土地へと向かいましたが、大きな魚に飲み込まれ、悔い改め、自らを主に捧げました。ペテロはイエスを知らないと三度口にしましたが、イエスの愛によって赦され、悔い改めて再献身しました。若いテモテは情熱をもってしても苦労、失望、恐れにとらわれていました。そんな時パウロは励まします。「神は私たちに、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。」(Ⅱテモ1:7)
私たちは信仰生活の中で落胆したり、主から離れてしまったり、立ち上がれなくなることがあります。そんな時初めの愛に立ち返り主が私たちをどう呼んで下さったかを思い返しましょう。このクリスマスの期間ハヌカの祭りを思いながら光の子として出て行きましょう。キリストの栄光を現わしこの世の暗闇との戦いに勝利しましょう。
≪分かち合いのために≫
- 光の子どもとして、打ち勝つべき闇の領域はありますか?
- イエス様はあなたに何を献げてほしいと願っていますか?再献身することは何でしょうか?
今日の暗唱聖句
「あなたがたは以前は闇でしたが、今は、主にあって光となりました。光の子どもとして歩みなさい。」 (エペソ人への手紙 5章8節)